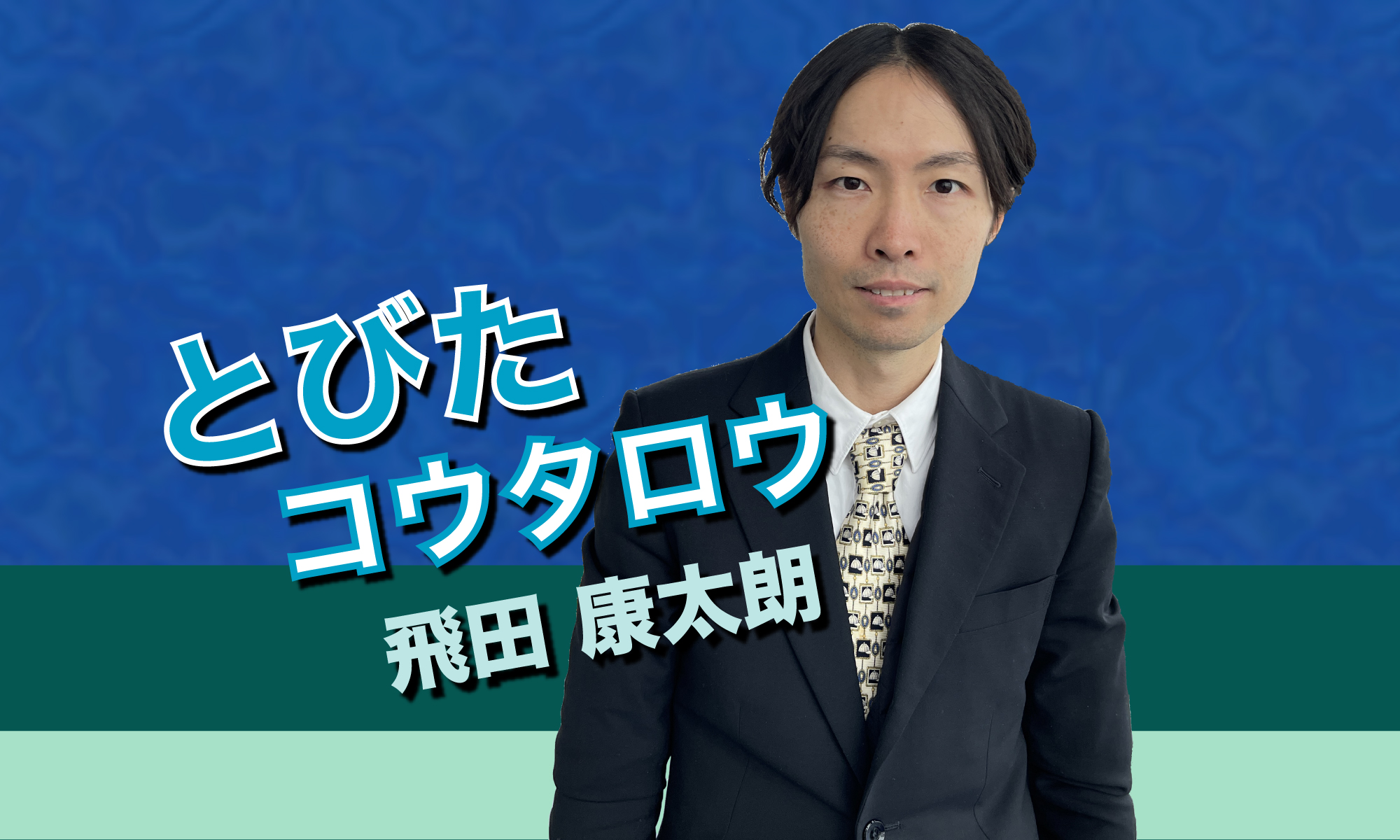東京23区内の一人暮らしの若者において、死亡してから発見されるまで0日〜1日以上要した者の数が過去3年間で742人いたという記事が7月22日の産経新聞の一面に掲載されていた。いわゆる孤独死というものだ。配偶者と死に別れた一人暮らしのお年寄りが陥る、というような認識をもたれがちだが、この記事では若年者も陥ると、深刻な実態を伝えている。
東京都に仕事を求めて若者が全国から移住してくる様は、一極集中などと呼ばれ改善すべき問題としてよく挙げられるものだ。仕事は手に入っても、一人の人間の人生に必要なもの全てを東京が与えてくれるわけではない現実を露呈しているように思う。これまでは違ったのかもしれないが、今は東京には孤独がありふれている。感覚では誰しも感じたことがあることが、数字で示されると思いがけずゾッとしてしまう。
孤独死が悪いから、死後すぐに発見できるようにしましょうということではない。社会との接点を失ってセルフネグレクト(自己放任)に陥ってしまうことが背景にあると分析されるらしいが、そうならなければいいという話でもない。昔は地域社会が発達していて孤独を防げていたから、昔のようになればいいというのも違う。良かった過去と同じものが今現れてくれることは決してない。孤独な人間を切り離していく社会が、最後の一人になるまで衰退する帰結を含んでいることの危機感を私たちは持つべきだ。
人間関係を得るのに職場に期待をかけるという考えはもはや、まったく時代遅れである。今回記事で取り上げられたような若者は、例えばアットホームな職場なんて避けるようなタイプである。日本経済の存在感がなくなり続けた30年を経て、職場は仕事だけをしにいく場所という傾向が強まった。十分な賃金が得られない非正規雇用の働き方は見本となるべき行政機関でさえ多い。民間の会社には社員への十分な賃金プラス何かを与えることを期待しましょうというのが、無理な話だ。雇用されて働く側だって自己実現まで会社に求めてないのだ。仕事を通して、生活の質と必要な人間関係を手に入れられる恵まれた人間だけが東京の全てではないと、若者の孤独死の実態は現していないか。
保育や介護のように、孤独対策についても、民間に期待するのでなく行政がもっと関わっていかないとどうにもならないことになってきている。そして、日本政府としても、社会全体の問題と捉えており、昨年は孤立死の実態把握を目的とした作業部会を開いていると記事には書かれていることを、記しておく。